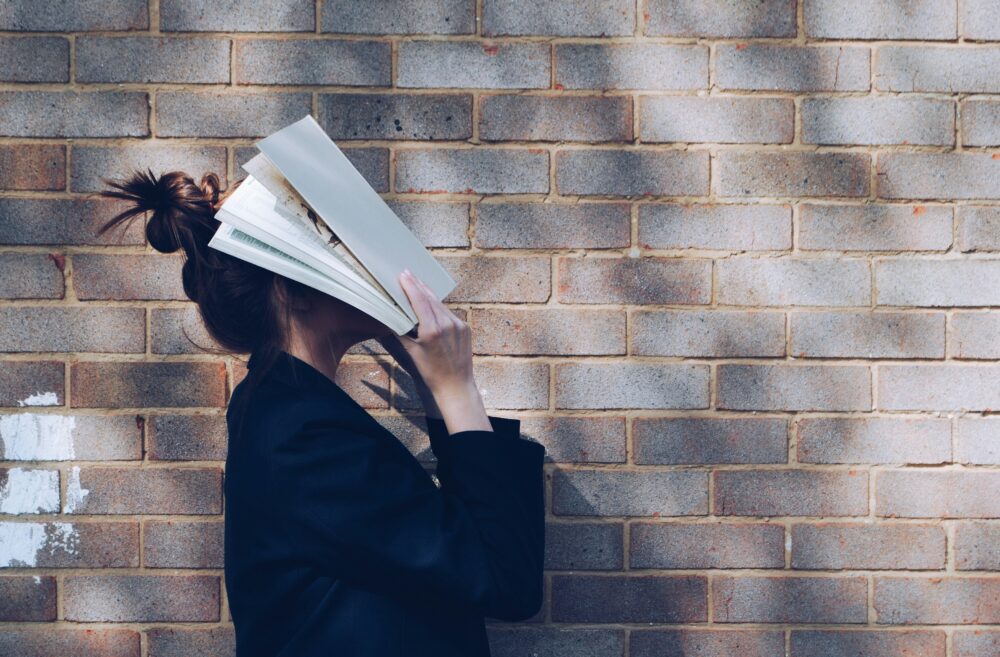1歳を過ぎても夜泣きが続くと、親は心身ともに疲れ果ててしまいます。昼間は元気いっぱい遊んでいても、夜になると頻繁に目を覚まし、泣いてしまう。そんな日が続くと、睡眠不足から体調を崩したり、育児への気力が落ちてしまったりすることもあります。
私も息子が1歳の頃、夜泣きに悩まされていました。毎晩のように起きては泣き、授乳や抱っこでやっと落ち着かせる日々。そんなとき、「生活リズムと寝かしつけを見直すことで改善できるかもしれない」と気づき、試行錯誤を重ねました。今回は、私の経験と調べた知識をもとに、1歳児の睡眠リズムを整える方法をご紹介します。
1歳児の夜泣きが起こる主な原因
成長や発達による睡眠リズムの変化
1歳前後は、脳や身体が急速に成長する時期です。歩けるようになったり、言葉を発するようになったりと、新しい刺激が多く、日中の興奮が夜の睡眠にも影響することがあります。また、睡眠サイクルが発達してくることで、浅い眠りと深い眠りの切り替えが頻繁になり、目を覚ましやすくなります。
昼寝や活動量の影響
昼寝が長すぎたり、夕方に遅くまで寝てしまったりすると、夜の寝つきが悪くなります。逆に日中の活動量が足りないと、体が十分に疲れておらず、深い眠りに入りにくくなります。
環境や生活習慣の乱れ
寝室が明るすぎたり、暑すぎたり寒すぎたりすると眠りが浅くなります。また、就寝時間が日によってバラバラだと、体内時計が乱れ、夜泣きの原因になることもあります。
睡眠リズムを整えるための生活習慣づくり
起床・就寝時間を一定に保つ
私が実践して効果を感じたのは、毎日ほぼ同じ時間に起き、同じ時間に寝ることです。休日や特別な日もできるだけ崩さず、体内時計を安定させることが大切です。
日中の活動量と日光浴の重要性
午前中に外遊びや散歩を取り入れると、夜の寝つきが良くなります。日光を浴びることで体内時計がリセットされ、自然な眠気が夜に訪れやすくなります。
昼寝の時間と回数の調整方法
1歳頃は昼寝が1〜2回の子が多いですが、午後遅くの昼寝は避けた方が夜の寝つきがスムーズです。私の場合、午前中に1時間、午後に1時間程度の昼寝に落ち着かせることで、夜泣きが減りました。
夜泣きを減らす寝かしつけの工夫
入眠儀式をつくる
毎晩同じ流れで寝る準備をすると、「これから寝る時間だ」と子どもが理解しやすくなります。私は、パジャマに着替える→歯磨き→絵本を読む→電気を暗くする、という流れを毎日繰り返しました。
寝室環境を整える(温度・光・音)
寝室の温度は夏は26〜28℃、冬は18〜22℃程度を目安にしました。真っ暗にすると怖がる場合は、間接照明や豆電球を活用します。外の物音が気になる場合は、ホワイトノイズや優しい音楽を流すと安心することがあります。
寝る前の過ごし方を見直す(刺激を減らす)
就寝前はテレビやスマホなどの光刺激を避け、静かな遊びに切り替えます。激しい遊びや興奮する活動は、寝つきを悪くする原因になります。
親も無理をしないためのサポート活用法
家族や周囲に協力を頼む
ワンオペ状態が続くと心身の疲労が限界に達します。私は夫に休日だけでも寝かしつけをお願いしたり、実家に泊まりに行ってサポートしてもらいました。
一時預かりやサポートサービスの利用
地域の一時保育やファミリーサポートなど、公的サービスも活用できます。短時間でも子どもを預けられると、自分の睡眠やリフレッシュの時間が確保できます。
親自身の休息時間を確保する方法
夜泣きの対応は避けられない日もありますが、昼間に子どもと一緒に仮眠を取るだけでも回復します。完璧に家事をこなすことより、自分の休息を優先することが大切です。
まとめ
1歳児の夜泣きは成長の一環であり、必ず終わりが来ます。しかし、その時期を少しでも快適に乗り切るためには、生活リズムの安定と寝かしつけの工夫が有効です。私も起床・就寝時間を一定にし、入眠儀式や環境調整を取り入れたことで、夜泣きの回数が減りました。
親も無理をせず、家族やサービスの力を借りながら、自分の心と体を守ることが大切です。少しずつでも睡眠リズムを整えていけば、子どもも親もぐっすり眠れる日が必ずやってきます。