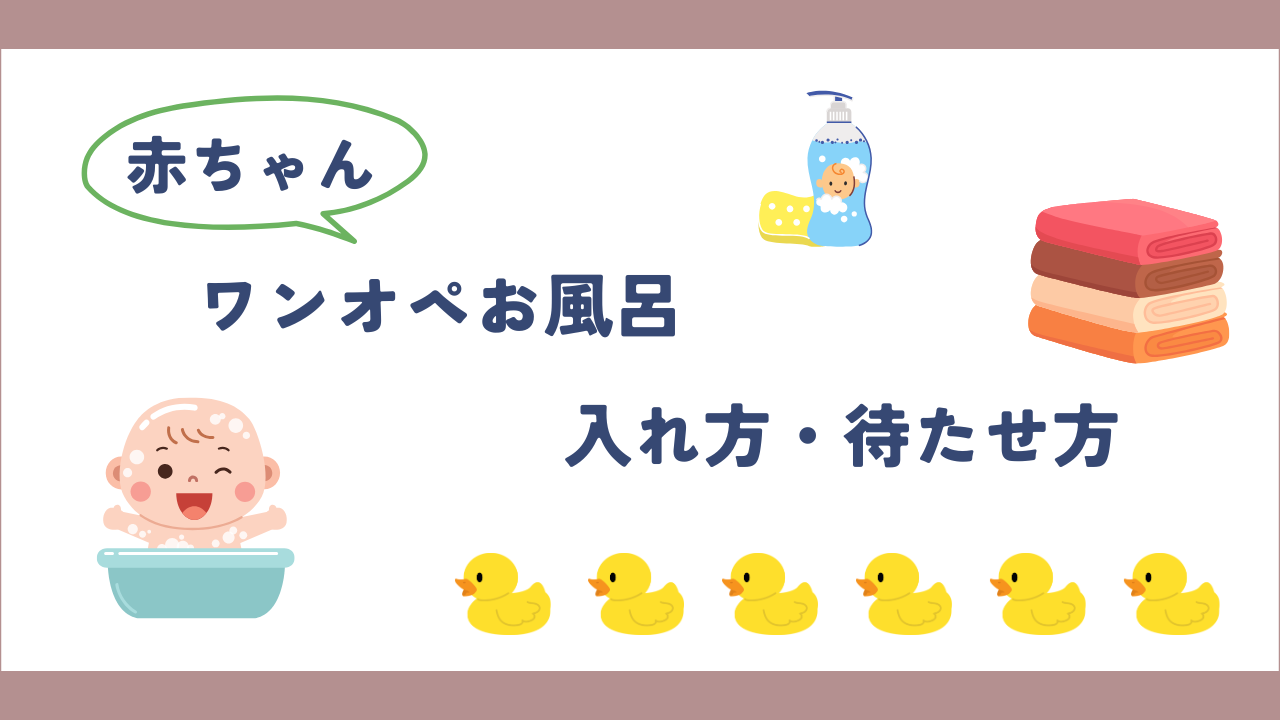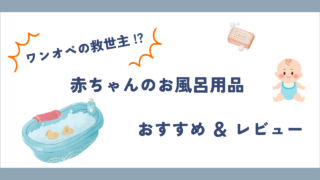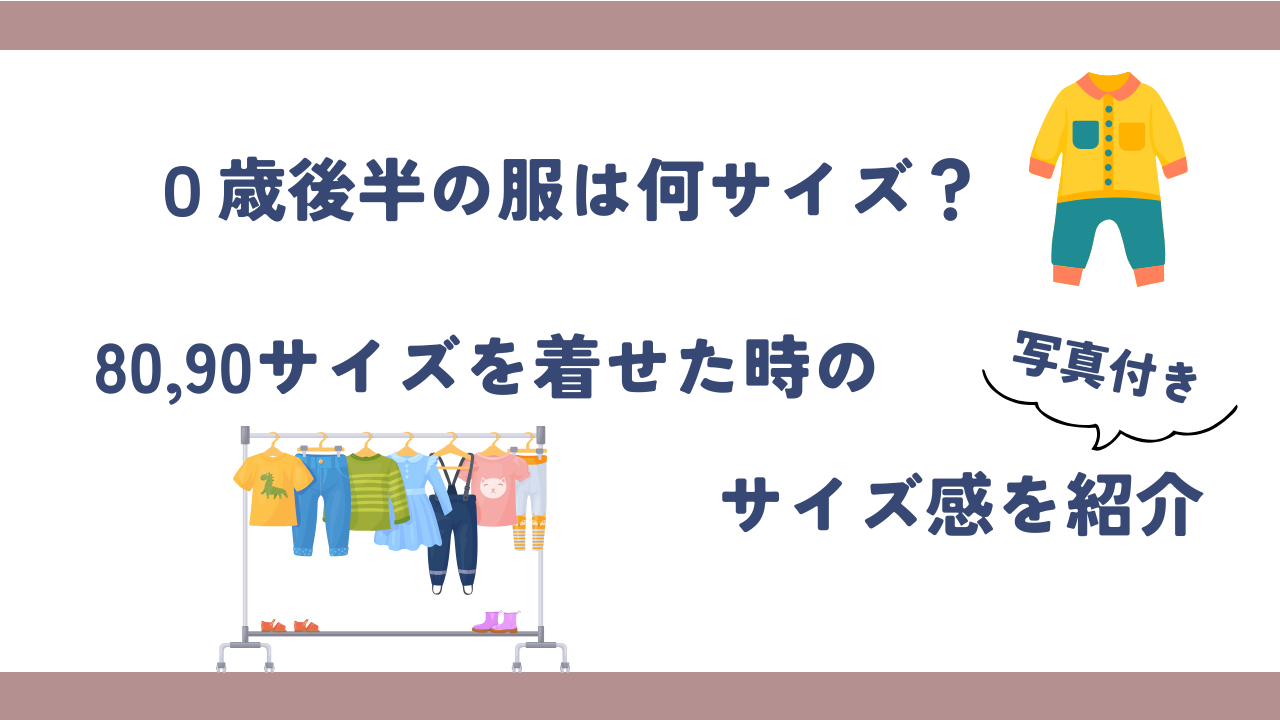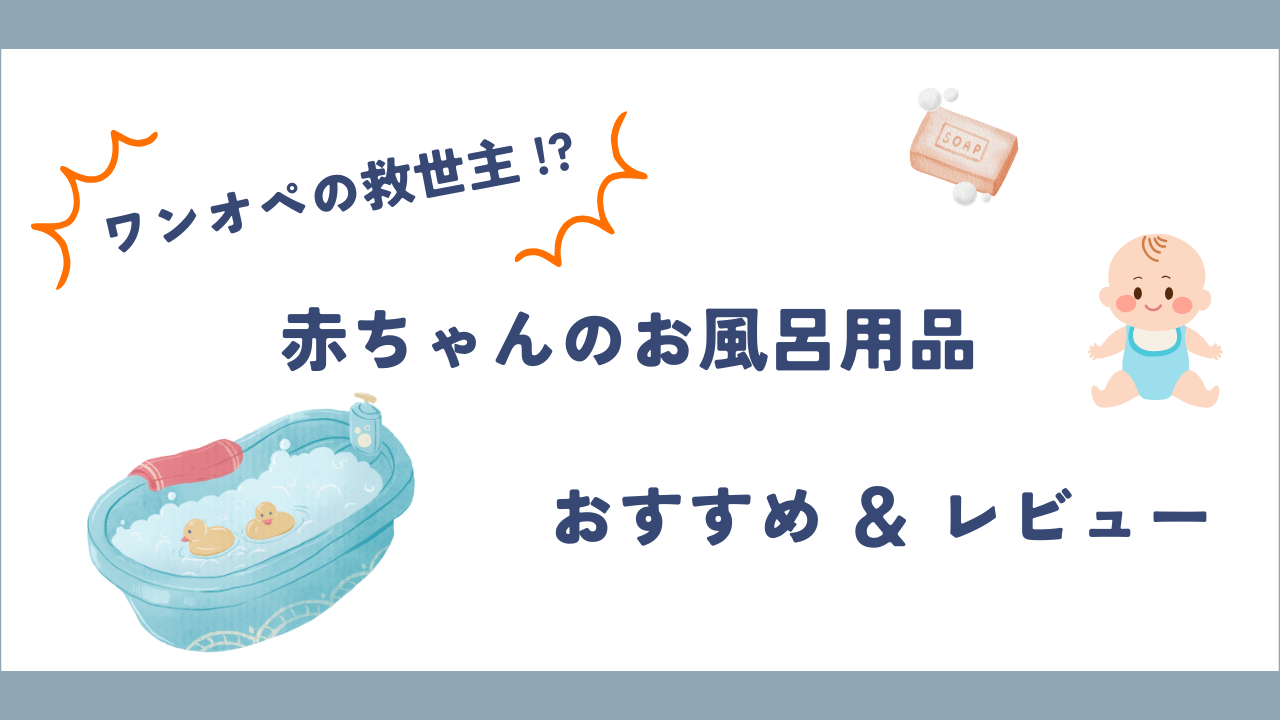はじめに
ワンオペ育児をされている方にとって、赤ちゃんとのお風呂は最も悩ましいことの1つではないでしょうか。
- 最初から一緒に入る?
それとも外で待っていてもらい、先に自分が入って途中から一緒に入る? - 最初から一緒に入る場合、自分が体を洗う間、赤ちゃんはどこで待っていてもらう?
- 大きい湯舟につける? それとも、ベビーバスにお湯をためる?
- お風呂をあがってからの赤ちゃんと自分の着替えは?
など、私は色々悩みの種が尽きませんでした。
我が家は現在、私が育休中で夫がフルタイム勤務中です。
夫の仕事が忙しいため、どうしても平日のお風呂はワンオペにならざるを得ません。
ワンオペお風呂の方法をいくつか試す中で、今のところ一番良いお風呂の入れ方を見つけましたので、本記事では時系列に沿ってご紹介したいと思います。
なお、ご参考までに夫と2人でお風呂に入れる時の方法もご紹介しますので、興味のある方は最後までお目通しいただけますと幸いです。
ワンオペお風呂
新生児~生後2か月
新生児の時は大人と一緒のお風呂に入れないため、ベビーバスを使って沐浴をしていました。
生後1か月以降は大人と同じお風呂でよかったのですが、ちょうど沐浴になれてきた頃だったので新しい方法に踏み切れず、生後2か月くらいまで沐浴をしていました。笑
使用グッズ
具体的に使用していたグッズは、以下の3点です。
- ベビーバス
- 沐浴ガーゼ
- スキナベーブ(沐浴剤)
沐浴場所
産院でもらったプラスチックのベビーバスをキッチンのシンクにはめて沐浴していました。
なぜ、お風呂場ではなくキッチンで沐浴をしていたかというと、以下3点の理由からです。
- 立った状態の高さでできるため、腰を曲げてしゃがむ必要がなく腰が楽だから
- リビングと繋がっており、暖房が効いている環境で洗ったり服を着せたりできるから
(時期は3~4月) - スペースがあって保湿や着替えをしやすいリビングが近いから
特に2の理由は大きく、当時住んでいた家のお風呂には暖房機能がなく、冷えて風邪を引いてしまうのではと心配だったため、暖かいリビングの空気の中でお風呂に入れてあげられるようにしていました。

こういった理由から、新生児期が終わっても生後2か月くらいまではキッチンでお風呂に入れていました。笑
ワンオペならではの苦労…
ここで、ワンオペで苦労した点についてお話します。
産院にはお湯につけるスペースと泡を洗い流すスペースがあったのですが、我が家のキッチンのシンクは1つでベビーバスをはめると埋まってしまうため、当然お湯につけるスペースしかありません。
沐浴初心者の私にとって、片手で赤ちゃんの姿勢を変えながらお湯から出して洗うのは難しく、かといってお湯につかったままだと泡がすぐに流れて上手く洗えませんでした。
さらに、上がる直前までお湯につけてあげたいと思っていたのですが、ベビーバスのお湯には体を洗った泡がたまっていくため、最後に泡を綺麗に洗い流せないことが懸念でした。
解決してくれたアイテム
そんな時に知ったのが「スキナベーブ」という沐浴剤です。
なんと、これ1本さえあれば、石鹸も洗い流しも不要という優れものでした!
スキナベーブを入れたお湯につけたガーゼで体をなでるだけで洗うことができ、また石鹸のように洗い流しが不要なので、赤ちゃんをお湯につけたまますべてが完結します。

片手作業で自由に手を動かせない私にとっては、とてもありがたかったです!!
入れ方
- キッチンのシンクにベビーバスをセットする
- ベビーバスにお湯をため、スキナベーブを入れる
- その間に、あがった後に使うバスタオル・保湿剤・肌着や服を用意する
- 赤ちゃんの服を脱がせてお湯につける
- 赤ちゃんのお腹が冷えないように、沐浴ガーゼをお腹にかける
- 片手で赤ちゃんの体を支え、もう片方の手で体を洗う
- 洗い終えたら、しばらく肩まで温もらせてからお湯からあげる
- コンロとシンクの間の作業スペースに置いたバスタオルで体を拭く
- リビングで保湿を行い、服を着せる
生後2~8か月
生後2か月頃より、体が大きくなってベビーバスが狭くなってきたことと、体重が増えて片手で支えるのが大変になったことから大人と同じお風呂に入れるようになりました。
使用グッズ
具体的に使用していたグッズは、以下の1点のみです。
- アラウベビー 泡全身ソープ

使用レビューや詳細はこちらの記事に記載していますので、興味があればご覧ください。
場所
先述のとおり、お風呂場です。
入れ方
大人のお風呂に入れるようになってからは、先に自分が入って一通り洗い、あとから赤ちゃんを入れる方式にしました。
- 浴槽内にお湯をためる or 追い炊きをする
- その間に、あがった後に使うバスタオル・保湿剤・肌着と服を用意する
- リビングに赤ちゃんの手が届く範囲に危ないものがあれば動かし、遊ぶスペースを作る
- プレイジムやお気に入りのおもちゃをセットし、リビングで遊んでいてもらう
- 急いで自分が先にお風呂に入る
- 顔の保湿やドライヤーまで終わったら髪を結び、服は着ずに裸のままリビングへ迎えに行く
- 赤ちゃんの服を脱がせ、一緒に浴室に入る
- 風呂椅子に座って、膝の上に向かい合せになるように赤ちゃんを乗せて洗う
- 一緒に湯舟につかる
- 脱衣所にあがったら、保湿を行い、服を着せる


2回浴室に入るという手間はありますが、先に自分が一通り終わらせてしまうことで、裸のまま赤ちゃんを待たせたり、赤ちゃんを保湿している間に自分の顔が乾燥でカピカピになるということがなかったので良かったです。
しかし、生後8~9か月頃から後追いが始まり、リビングで1人になると大泣きするようになってしまったため方法を変えることにしました。
生後9か月~
後追いが始まり1人になると大泣きするようになったため、最初から一緒に入ることにしました。
結論として、最初から一緒に入るこの入れ方が今のところ最も良いです。


一時的であっても赤ちゃんを1人にすることがなく安心なため、思えば大人のお風呂に入れ始めた生後2か月の時からこうすればよかったと思います。笑
使用グッズ
具体的に使用していたグッズは、以下の2点です。
- アラウベビー 泡全身ソープ
- 風呂マット




風呂マットに関する使用レビューや詳細についても、こちらの記事に記載していますので、興味があればご覧ください。
場所
これまでと同じく、お風呂場です。
入れ方
- 浴槽内にお湯をため or 追い炊きをしながら、浴室内の暖房を入れる
- その間に、あがった後に使うバスタオル・保湿剤・肌着と服を用意する
- 自分の服をすべて脱いだ後に赤ちゃんの服もすべて脱がし、一緒に浴室に入る
- 風呂マットを奥ではなくドア側に置き、赤ちゃんを風呂マットの上に寝かせる
- 赤ちゃんと向かいあわせに座り(ドア側を向く)、時々赤ちゃんにお湯をかけながら自分を洗う
※赤ちゃんの様子を随時見られるようにするためと洗い流す時の水がかかりにくいようにするため - 風呂マットに寝かせたまま赤ちゃんの体と頭を洗う
- 一緒に湯舟につかる
- あがったら赤ちゃんをバスタオルの上に置き、自分は最低限の水気を拭く
※私は髪の毛が長いため、この後バスタオルを頭に巻いています - 赤ちゃんの保湿を行い、服を着せる
※この間に自分の顔がカピカピに乾いてくるため、手についた保湿剤を顔に塗るのがおすすめ笑 - 脱衣所で待っていてもらいながら、自分の保湿と着替えを行う
最初の頃は風呂マットに置くと泣いていましたが、水にぬれても大丈夫なお気に入りのおもちゃを持たせることで落ち着いてくれました。


今では慣れてくれて、何も持たせなくても泣かずに私の様子や浴室内を観察しています。笑
<参考>夫とツーオペお風呂の入れ方
新生児~生後2か月
キッチンのシンクにベビーバスをはめてお風呂に入れることや全体的な流れは同じで、1人が赤ちゃんを支える係・もう1人が体を洗う係としてやっていました。
生後2か月~
2人いる時は、浴室内と浴室外に分かれて担当しています。
- 浴槽内にお湯をためる or 追い炊きをする
- その間に、あがった後に使うバスタオル・保湿剤・肌着と服を用意する
- 夫に赤ちゃんを見ておいてもらい、自分が先に入って洗う
- 洗い終わったら、夫に赤ちゃんの服を脱がせてもらい、浴室に連れてきてもらう
- 風呂椅子に座って、膝の上に向かい合せになるように赤ちゃんを乗せて洗う
or 赤ちゃんを風呂マットに寝かせて、赤ちゃんの体と頭を洗う - 一緒に湯舟につかる
- 夫を呼んで赤ちゃんを受け取ってもらい、保湿を行ったり服を着させてもらう
- 自分もあがって保湿や着替えを行う
やはりワンオペの時と違い、圧倒的にやりやすいです。


人間1人お風呂にいれるだけでも大変だなぁと思いました…
まとめ
以上が我が家のワンオペお風呂の方法でした。
1人で立ったりある程度洗えるようになるともう少し楽になるのかもしれませんが、すべてにおいて補助が必要な現在は、1日の中でワンオペお風呂が一番大変な気がします。
とはいえ、長い人生においてここまでしてあげられるのも今だけなので、この時間を大切に過ごしたいなと思いました。
ワンオペお風呂の方法を悩まれている方の負担軽減に、少しでも参考になれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。